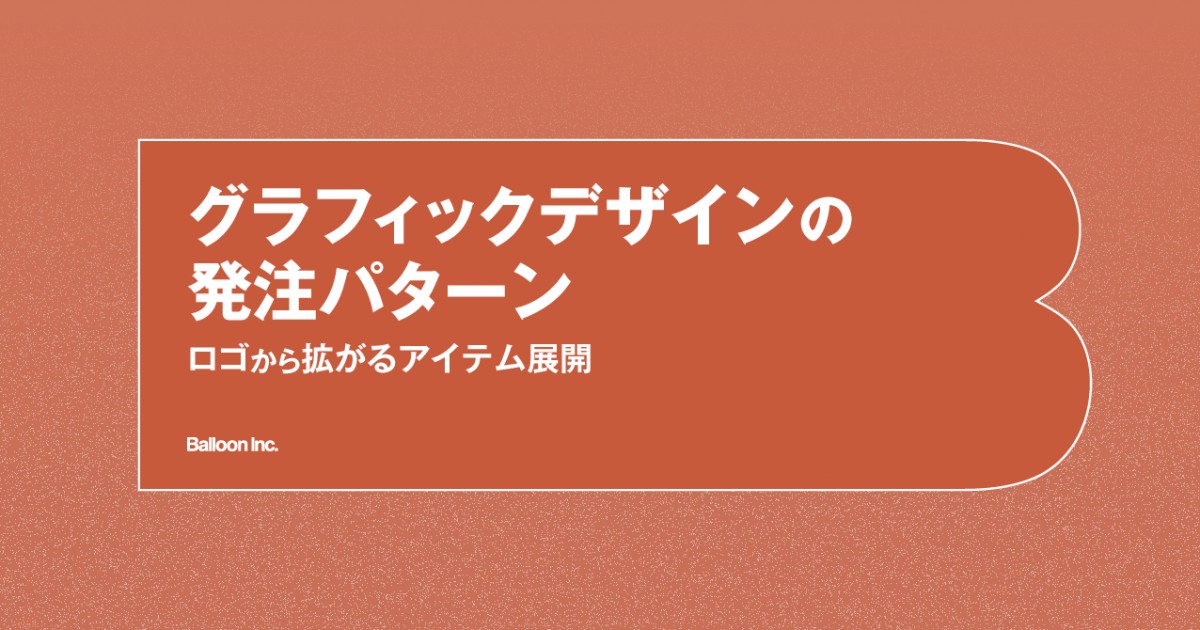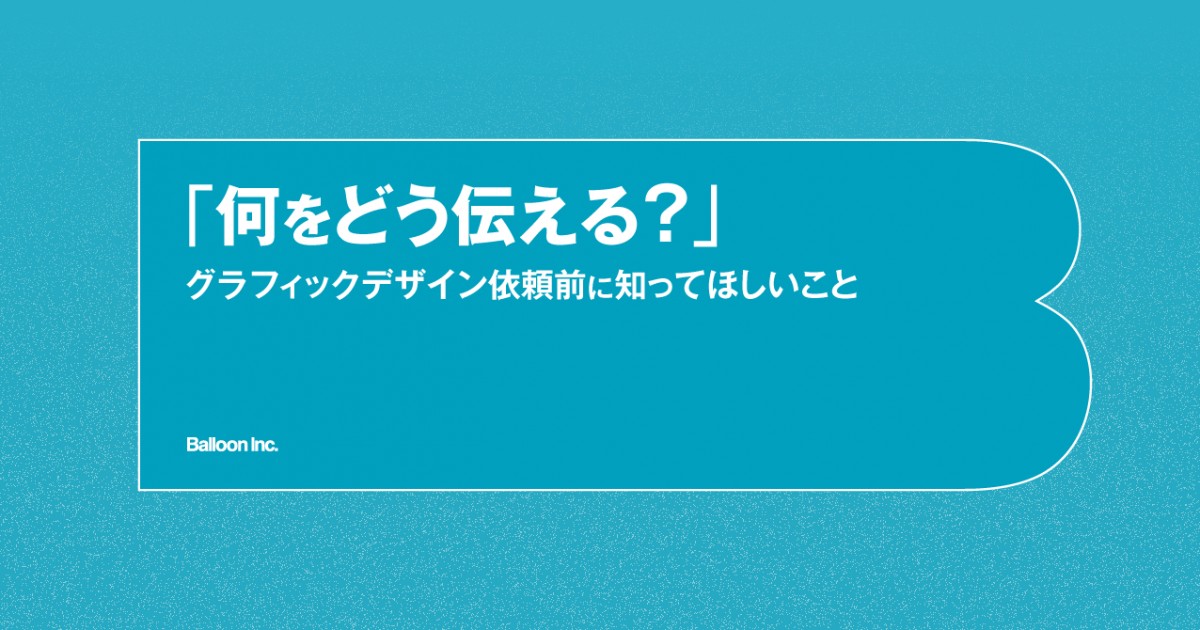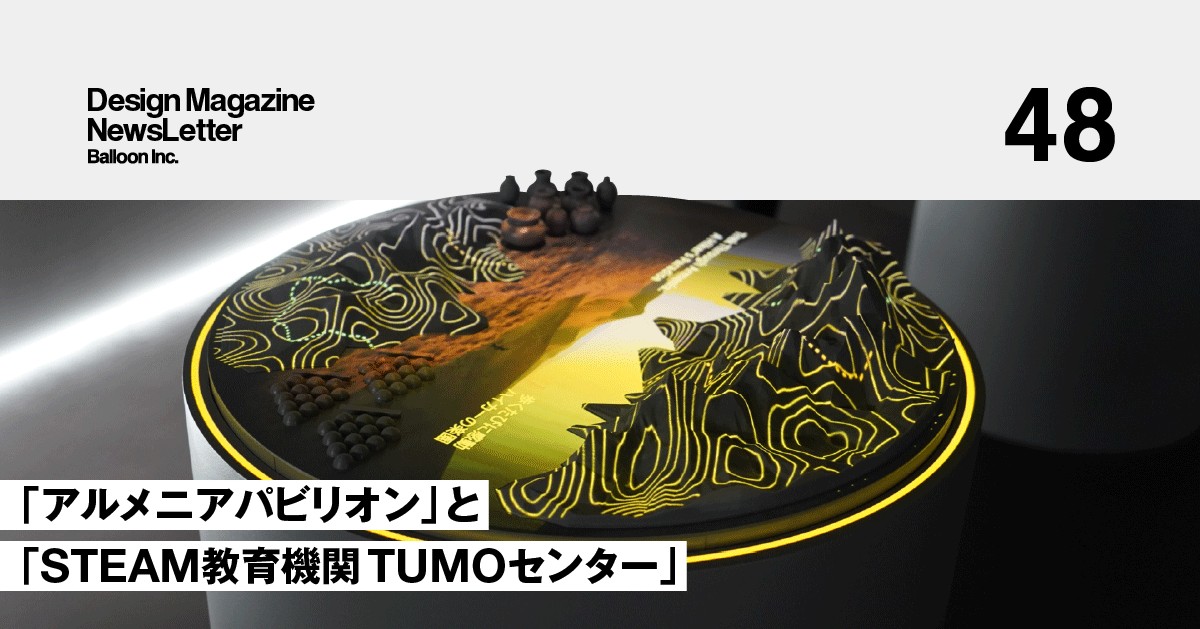デザインマガジン🎈Balloon vol.52「補聴器のデザイン」と「音の左右を示す色の秘密」
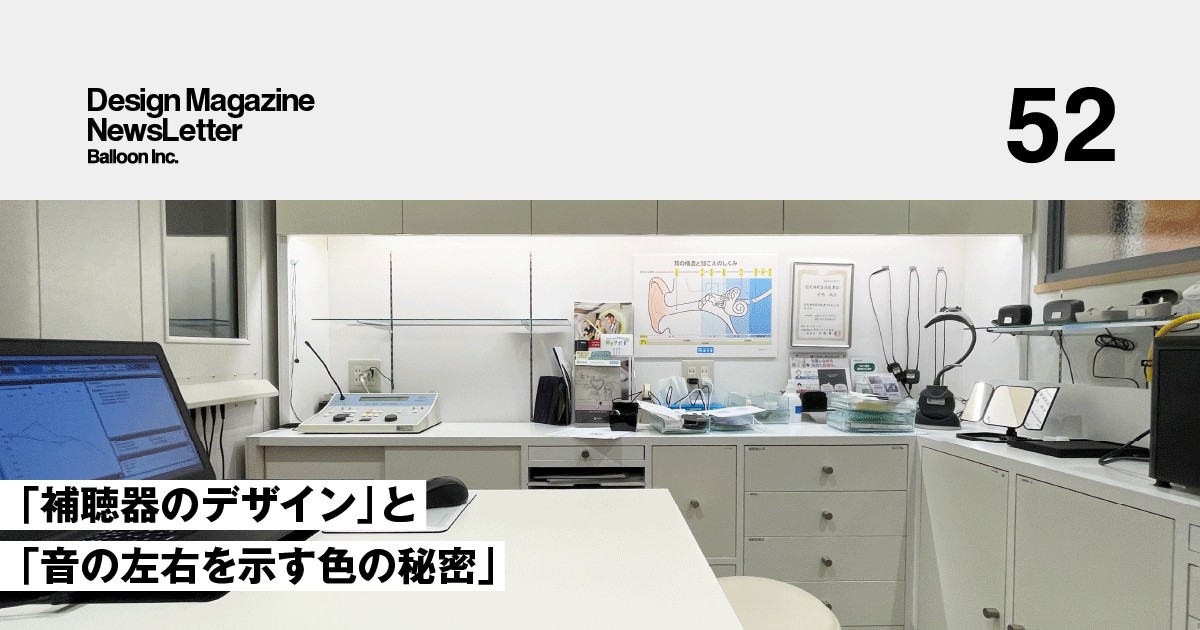
ブランディング・UX・グラフィック・プロダクト・UI・Webサイトなどクリエイティブ全般をカバーするデザインコンサルティングスタジオ Balloon株式会社がお届けするデザインマガジンです。
メールマガジンにご登録されていない方はこちらからご登録いただけますとうれしいです!
日常に潜むデザインの疑問
つい先日、補聴器を間近で見る機会がありました。それまで知らなかったのですが、補聴器の本体には右耳は赤色、左耳は青色と色分けすることが義務づけられているそうです。
日常生活の中で、私たちは無意識のうちに多くのデザインに触れています。その中には、一見すると単純な形状やカラーリングに見えても、実は様々な理由に根ざしたものが少なくありません。
今回は、この補聴器の赤と青の色分けがなぜ採用されたのか、そしてそのルーツがどこにあるのかという疑問を調べました。
補聴器における色分け:ユーザー体験と機能性
左右の機器にマーキングをすることで、適切な使用を促すという点で、このカラリングはユーザー体験を補助していると言えそうです。
補聴器の主なユーザー層には高齢者が多く含まれるため、細かい文字の識別が困難な場合があります。赤と青という対照的で区別のしやすい色は、視覚的に最も区別しやすく、直感的な識別を可能にします。
とは言え疑問なのは、右耳は赤色、左耳は青色という色を採用した理由です。「右=赤」ということをあらゆる状況において直感的に認識できる理由は見当たりません。
例えばこうした配色に関する公式な国際標準などでも規格化されているものでは無いようです 。一方で多くの主要メーカーが赤は右、青は左を共通して採用しているということは、業界内での「デファクトスタンダード」(事実上の標準)として広く受け入れられていることを示唆しています。
そうしたデファクトスタンダードとして受け入れられていった経緯を調べていくと、既存の「オーディオ業界の色分け慣習」を引用することでユーザーの学習コストを下げ、製品の利便性と安全性を高めていったデザインの工夫と歴史がありました。
音声ケーブルの歴史と「赤は右」の起源:RCAコネクタ
補聴器の左右識別における赤と青の色分けのルーツを辿ると、音声信号伝送の歴史、特にRCAコネクタの進化に行き着きます。
RCAコネクタは、1930年代にRadio Corporation of America(RCA)によって開発されました。当初、「フォノコネクタ」とも呼ばれたこのコネクタは、ラジオ蓄音機とアンプを接続するためのモノラル(単一チャンネル)オーディオ専用として設計されたものです 。
それ以前の音声接続は、むき出しのワイヤーやネジ端子を扱う必要があり、かさばり、高価で使いにくいものでした。RCAコネクタは、コンパクトで差し込みやすく、製造コストも低いという点で画期的なソリューションであり、消費者向け電子機器に最適でした 。
1950年代に入り、ステレオサウンドが一般に普及し始めると、音声信号は左右の2つの独立したチャンネルに分割されるようになりました。これにより、RCAコネクタも左右のチャンネルを区別する必要が生じました。RCA社は、既存のコネクタデザインを適応させ、単に2本目のケーブルを追加することでこの変化に対応しました。
◉「赤は右、白は左」の慣習が生まれた背景と「Red is Right」の語呂合わせ
このステレオ化の際に、ユーザーが容易に識別できるよう色分けが導入されます。右チャンネルには赤色、左チャンネルには白色(または黒色)が割り当てられました 。これは、ユーザーがケーブルを正しく接続できるようにするための、極めて実用的な解決策でした。
「Red is Right」(赤は右)という覚えやすい語呂合わせは、この色分けの普及に大きく貢献し、今日まで続く強力な慣習となりました 。
興味深いのは、こうした配色の決定が、特定の国際機関による標準化プロセスを経て確立されたものでは無いという点です。
RCA社という一企業が、ステレオサウンドの普及という市場のニーズに対応するために、既存の技術(RCAコネクタ)を適応させた実用的な解決策として色分けを導入しました 。この色分けは、その利便性と「Red is Right」という覚えやすい語呂合わせによって、消費者や業界関係者に広く受け入れられ 、結果として業界全体のデファクトスタンダードとして定着しました。
これは、技術的優位性だけでなく、ユーザーフレンドリーなデザインが標準化を推進する強力な要因となることを示す好例だと思います。企業主導の革新が市場の変化とユーザーの受容を通じて、事実上の標準を形成する典型的なパターンですね。
現在ではRCAケーブルが使われるシーンは少なくなっており、HDMI等に移行していますが、そうした多様化したケーブルのカラーについてはConsumer Electronics Association (CEA) によって以下のように規格化されています。
補聴器の左右識別では、右耳が「赤」であるのに対し、左耳はRCAステレオの「白」ではなく「青」が採用されています。上図の色規格を見ると「サラウンド左:青」と記載されていますが、こういしたオーディオ信号の「左」を示す色として使われている「青」を採用したようです。
色分け標準化の意義と普遍性
色分けは単なる識別子ではなく、普遍的な「言語」として機能します。文字や記号が読みにくい状況、あるいは言語の壁がある状況において、色は瞬時に情報を伝達する強力なツールとなります。
どのケーブルをどこに繋ぐか、どの部品がどのような機能を持つかを、ユーザーや技術者が直感的に理解できるようにします。RCAケーブルや補聴器の色分けは、この「色の言語」が技術とデザインの交差点でいかに効果的に機能するかを示す好例であり、ユニバーサルデザインの原則にも通じる、デザインの持つ強力なコミュニケーション能力を象徴しています。
補聴器の右耳が赤、左耳が青という色分けは、単なる偶然やデザイン的な選択ではなく、長年にわたるオーディオ業界の慣習とユーザーの利便性への配慮がによって受け入れられていったものでした。
この色分けは、補聴器という精密な医療機器においてユーザーが左右を迷わず正しく装着するための補助的な機能的役割を担っています。これは、デザインが単なる見た目だけでなく、製品の使いやすさ、安全性、そして信頼性を高める上でいかに不可欠であるかを雄弁に物語っています。
日常のささやかなデザインの中に、技術の進化や産業の標準化、そしてユーザーへの配慮といった理由が隠されていることを再認識させらる興味深い例ですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!デザインマガジン🎈Balloonは毎月2回配信予定です。本メールマガジンの感想や質問などをSNSに投稿していただけると嬉しいです。次回もお楽しみに!
すでに登録済みの方は こちら